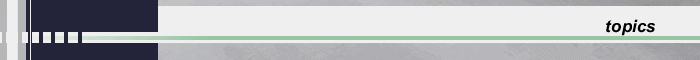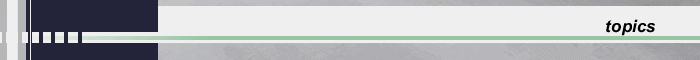���������ۑ�w����
�\�w��̎��R�Ƒ�w�l�̘A�сA�����ċ��|����̎��R�\�@
���������ۑ�w�O�������x������S���A������ǒ��@�@�d�{������
��������Ă���̂�
2002�N3��29���ɔ����������������ۑ�w�ɂ�����O�����������َ����ւ̎��g�݂����P�N�����߂����B���̊Ԃ̎x���̎��g�݂̒��ŁA���̒������ق����ۓI�ȍ���������v�̗���ɐ^��������t�s���鐫�i�̂��̂ł��邱�Ƃ��Љ�I�ɖ��炩�ɂȂ����B���Ȃ킿�A���̎����́A�w����o�c���������E������e����ы����R���ɒ��ډ��������ɂ���𗝗R�ɉߍ��ȏ��������s�������̂ł���A���{�̑�w�̒������j�̒��ł��H�L�̋����ׂ������ł���Ƃ������Ƃł���B���̂��Ƃ́A��w�l�̐l���܂苳�猠�E�������̐N�Q�����ł���A����ɂ͊w���̏������̐N�Q�ɂȂ��鎖���ł���ƌ�����B�����ł͊w��̎��R�Ƒ�w�l�̐l���������w�̑����̍���������Ă���B�܂��A���l�X�R21���I��������錾���͂��߂Ƃ������ۓI�������ɂ����鋳���̐l���i���猠�E�������j�̑��d�A����ɐE���E�w�����܂߂���w�\�����S���̑�w�^�c�ւ̎�̓I�Q���̕������Ƌt�s���鎖���ł�����B�����̏ڍׂȐ��i�ɂ��Ă̕��͂́A���Ɍ��J�E���\����Ă���g�o�Ghttp://www.jca.apc.org/~k-naka/�A�w���{�̉Ȋw�ҁx2003�N2�������Q�Ƃ��ꂽ���B�{�e�ł͓��{�̑�w��������Ă����荪���I�ō����I�Ȑ��i���玭�������ۑ�w������ǂ݉����Ă��������Ǝv���B
���������ۑ�w��������݂��Ă������
���������ۑ�w�ɂ�����ɂ߂Č����Ȋw���ւ̌����W���A����͊w����e�ɂ܂œ��ݍ��u�ƍٓI�E���Ў�`�I�̐��v�ƌ����Ă��悢�ł���B���݁A����������w���킸�A��w�^�c�͂��̌������w���E�������֏W��������X���ɂ���B�����̏W���́A�����`�̐[���E�O��Ƒ����s���āi�\����̂̉��Łj�i�ނ��Ƃɂ���Ă͂��߂ď\�S�ɋ@�\������̂ł���B�������A���������ۑ�w�����͐l�������܂ߌ����̏W���݂̂��ɒ[�ɐi���Ƃɂ���Đ������ے��I�Ȏ����ł���B���Ɏ�����w�ɂ����ẮA����A������Ȃ�тɋ����̋���E�������e�ւ̐N�Q���Ⴊ�������钛������悤�ɂȂ��Ă���B���݁A���̂����ꕔ���\����ɏo�Ă��邪�A�����͕����ꂽ�܂܂Ŏ�����������Ă���B���������l���N�Q�́A������w�́u�Ɨ��s���@�l���v�ɂ���č����������A���{�̍�������S�̂ɋy�Ԃ��Ƃ��\�������B�܂��A���Ă̐펞���ɗނ���悤�ȍ��Ǝ�`�i�i�V���i���Y���j�I�ȃv���W�F�N�g�Ƃ��Č����E���炪�����Â����悤�Ƃ��Ă���B�����������Ԃ̐i�s�͖��炩�ɍ��ۓI�����ɋt�s�������̂ł���A�ꍑ�̌o�ϓI�����͂̂��߂ɍ�����������҂��悤�Ƃ�����̂ł���B����͍��ۓI�Ǘ������������邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�����ł͌����E����̕]�������܂߁u�w��̎��R�v�ւ̐N�Q�A�w��̎������̊�@����������B���̂��Ƃ́A��w���ł̌��_�E�v�z�̎��R�̐N�Q�ɂƂǂ܂炸�A����A�����̌��_�E�\������юv�z�̎��R���̂��̂����������̂ł�����ƌ�����B�܂��A�����̍����̐l������w���ł̐l���ɔ��f���Ă�����B�w���Ɗw�O�̗��҂͑��݂ɍ�p���đ�w���ɂ�����u�ƍٓI�E���Ў�`�I�̐��v�Ɛl���N�Q���i�s���Ă���ƌ�����B���A���E�I�ɂ݂Ă������҂̐l���i��͏d�v�ȉۑ�ƈʒu�Â����Ă���B����܂łȂ炠�܂���グ���Ă��Ȃ����������҂̐l���i�삪�d������Ă���̂́A��������̕��y�A�Љ�I�e���͂̊g��Ƃ��������̔��f�ł���ƌ�����B1993�N5���Ƀ��V���g���Ō������ꂽ�u���A�J�f�~�[�E�w�p������̍��ېl���l�b�g���[�N�v�i�h�g�q�m�j�́A���ۘA�����̑��������E�l���錾�Ɋ�Â��Ȋw�҂̐l���i��̊��������ۓI�ɓW�J���Ă���B���{�w�p��c�������A���{�@�ւł���̂ɃI�u�U�[�o�[�Ƃ��Ă̎Q�������F�߂��Ȃ��������A�ŋߐ����ȃ����o�[�Ƃ��Č}�����邱�ƂɂȂ����悤�ł���B���l�b�g���[�N�̎��s�ψ��ɂ̓m�[�x����҂�����A�˂Ă���B�����҂̐l���i��͍��␢�E�I�l�b�g���[�N�Ƃ��ēW�J����悤�Ƃ��Ă���B�����A��w�R�c��\�Ɠ��N�����ɔ��\���ꂽ���l�X�R�u21���I��������Ɋւ��鐢�E�錾�\�W�]�ƍs���\�v�i1998�N10���j�́A����̎Љ�I���ۑ�ւ̎��g�݂Ə����̉����ɂނ��āA�u�w��̎��R�v�Ɋ�Â���w�̖��������炩�ɐ錾���Ă���B����Ƀ��l�X�R�́u��������̋���E���̒n�ʂɊւ��銩���v�i1997�N�j�ɂ����đ�w�����̌��i�Ȑg���ۏ�����߂Ă���B�Ȃ��A���݁A���l�X�R���������͓��{�l�ł��邱�ƂL���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���l�X�R�錾�����܂������Ȋw�Ȃɂ����Ė|�ꂸ�A�W�����������{�����ōL��E���y����Ȃ����Ƃ́A�����������Ƃ��Ă��̐ӔC�͏d��ł���B����͓��{�̍������琭���l�X�R�錾�̑ɂɕ����Â����Ă���̂ł���B
�w��̎��R�ƌ����҂̐l��
�����������Ԃ̐i�s�̒��A���������ۑ�w�O�������x������S���A����́A2003�N9��21���u�w��̎��R�ƌ����҂̐l���\���ۓI�����Ɠ��{�̉ۑ�A�����Ēm���l�̖����\�v�Ƒ肷����J�V���|�W���E�����J�Â����i���^�c�̂́A����������w���E���g���A���A�Љ���w��A���{�Ȋw�҉�c���s�x���A�쓇�ΗT������x������w�����̋��猤���Ɛg���ۏ���l�����ł���j�B���̃V���|�W���E���́A���A�̍��ېl���錾����ѐl���K��Ɋ�Â����E�I�Ȓ������ӂ܂��āA���ǖʂł̓��{�ɂ������@�I�ȁu�w��̎��R�ƌ����҂̐l���v�̏�����э���̍�������A�m���l�̂�����E�������c�_���邱�Ƃ��ۑ�Ƃ��ĊJ�Â��ꂽ�B�܂��A���݁A��w�ŋ�̓I�ɋN�������l�����̉����Ɏ����錤���҂̍����O�̘A�сi�l�b�g���[�N�j���߂̃V���|�W���E���ɂȂ邱�Ƃ����҂��ĊJ�Â��ꂽ�B�u��������̍��ۓI�����Ɠ��{�̑�w���v�v�Ƒ肳�ꂽ�c�����l���i���s��w���_�����A�l�Ԕ��B�����������j�́̕A�u�f�B�[�v�j���O�E�f���N���V�[�i�����`�̐[���E�O��j�v�Ƃ������_���������ꂽ�B��������̐��E�I�����ւ̕]���E�m�F�ł���B��w�R�c��\�A�Ɨ��s���@�l���Ƃ����������I�ȗ���̒��ŁA����ȊO�̎w�j�E���������Ă��Ȃ������̌���ɑ��A���ۓI�������w�юw�j�Ƃ��邱�Ƃ̈Ӌ`�ł���B���́A�u�w��̎������̊�@�ƒm���l�̖����v�Ƒ肳�ꂽ�I�t�q���i���m��w�������j�́̕A����E������̂̑��̎��_���烉�W�J���ɑ��_����N���ꂽ�B���܂⎀��ƂȂ��Ă���u�m���l�_�v�̍ċ��ł�����B�m���l�Ƃ��Ă̑�w�l�̎Љ�I�ӔC�Ƃ͉����ł���B��O�́A�u������w�Ɨ��s���@�l�����Ƒ�w�̎����Ɗw��̎��R�v�Ƒ肳�ꂽ�r�������i���É���w�����A��w���v���l����A�s�[���̉�Ăт����l��\�j�́̕A������w���u�m�̊�Ƒ́v�ւƑ傫���ǎ��������卑�ƃv���W�F�N�g�̐i�s�Ƃ������Ԃւ̌x���ł���B�Ɨ��s���@�l�����̖��m���ł���B����͊w��̊�b�����������ɂ���錻���ւ̌x���ł�����B��l�́A�u���{�ɂ����錤���҂̐l���ƍ���̉ۑ�v�Ƒ肳�ꂽ�l�ѐ��v���i�ꋴ��w���_�����A�i�r�`�Ȋw�҂̌������ψ���ψ����j�́̕A�u��w�̌o�ω��E��Ɖ��v�Ƃ�����卑�ƃv���W�F�N�g�ɑ��āA�����҂̐l���N�Q������ɑ������邱�Ƃւ̌x�����A�S���I�Ȍ����҂̘A�сi�l�b�g���[�N�j�Ƃ����ۑ���N�����B����ɂ́A�܂������҂̐l���i���猠�E�������j�N�Q�̌����ɂ��Ă̗��������߂��Ă���Ƃ����B�l���N�Q�ɂ��Ė������ɂȂ�����w�l�ւ̌x���ł���B�ȉ��ɂ����āA�����V���|�W���E���̎l���̕���ѓ��_����S�̘_�_�𒆐S�ɂ��āA���������ۑ�w�����̖�萫�i������ɓǂ݉����Ă������Ƃɂ���B
�����`�̐[���E�O���@
�����`�̐[���E�O��i�f�B�[�v�j���O�E�f���N���V�[�j�́A���ɁA���������]�ސl�́A���ł��A�N�ł��A�ǂ��ł��A�K�v�Ȏ��Ɋw�ׂ�Ƃ����ʒu�Â����Ă���Ƃ����_�ł���A���̓_���A���l�X�R�錾�ł́A�u���ފw�̏_��v�A�u�l�I�Ȕ��B�v�A�u�Љ�`�̕����ɂ�����l���v�A�u�����`�ƕ��a�̂��߂̋@��̒v�ɂ����ċ�̉����Ă���B��������ɂ����āA�u�ᔻ�I�Ői���I�ȋ@�\�̋����v�A�u�w��̎������̋���v�A�u�Љ�I�ӔC����ѐ����ӔC�v�������߂Ă���B��̓I�ɂ́A��w�ł̌����E���炪�A���ɕn���A�s���e�A�\�́A���A�Q��A����������ѕa�C�Ƃ������u���̈�Y�v�̍������������Ƃ����ۑ�Ɍ��������A�����`�Љ�Ɋ��S�ɃR�~�b�g���A�����Ɛ��`���琬����ϊv�̐��i�҂ƂȂ�悤�w���̔��B��ۏႵ�Ă����Ƃ����ۑ�ł���B���ېl���K��ł́u��������̖����������v�͂��̂��߂̊�b�I�����ƂȂ�B�������A�ˑR�Ƃ��Ă��̌����ɑ��ē��{���{�͗��ۂ��Ă���i���A�̎Љ�ψ����2006�N�܂łɗ��ۓP��ɂ��Ẳ���{���{�ɔ����Ă���j�B����ɍ�����w�̓Ɨ��s���@�l���ɂ���Ă��̖��������͊g�U�����댯��������B�����������킸��w�̌o�c��Ղ�����ǂ�����Ă����̂��A���̓_��I�ɋc�_���Ă����K�v��������Ă���B�������A�����͗Ⴆ�Ε����Ȋw�Ȏ哱�́u��w����x���i�b�n�k�j�v�ɂ݂���悤�ɁA������u�l�I�����Ƃ��Ă̔\�͊J���v�Ƃ����ϓ_����������A���ۓI�����Ƃ��Ă̐l�ԂƂ��Ă̐����E���B���ۏႳ��鎋�_���������Ă���B�b�n�k�̍̑�80���A�\����600�����Ă���A�킸��3�T�Ԃŏ��ʂƃq�A�����O���s���Č��_���o�����B�����ł͑O�q�̔��B�ۏ�Ɓu���̈�Y�v�̉����Ƃ������_���������Ă���B�f�B�[�v�j���O�E�f���N���V�[�𐄐i���邽�߂ɁA�c�����l���͂S�̎��_���������B�@�����𗥂��Љ�I�Ɏ�������A�A����ł͂Ȃ����Y���������w�ԁA�B���x��p�~������������I�E�p���I�ɕۏႷ��i�g�����W�V�����ۏ�j�A�C�Ƒ��̖����A������ʂ��Čl�̒��ɔ��B�ۑ���ʒu�Â���Ƃ������_�ł���B����������w����ɑ���]�����o�c������̐l�I�����J���Ƃ����ϓ_�ł͂Ȃ��A���͎Љ�I�ɘA�т��������Č`�����Ă������l�̂��߂̖����`�I�ȑ�O�ҕ]�������߂Ă���B����E�����݂̂Ȃ炸���x����ы@��̖����`�I�[���E�O��́A���{�̑�w���v�̐؎��ȉۑ�ł���A���������ۑ�w���������������̊Ԃ̊w���𒆐S�Ƃ����w�����v�Ƃ̑��_�̑��͂����ɂ���B�܂莭�������ۑ�w�ł̌��Ў�`�I�^�c�ł���B�����ł́A�w��̌ŗL�̓��ݓI���l�ɂ���Ăł͂Ȃ��O�ݓI�Ȍ��͂�АM�ɂ���ĉ^�c���邱�Ƃł���A��w���ł̐l�ԊW���㉺�W�E�ʊK���I�����ő����A��ɑ��Ă͋����I�ɒǏ]�E���]���A���ɂ͘����E����ɂӂ�܂��Ƃ������Ƃ��x�z�I�ȑ�w�^�c�ł���B����̓f�B�[�v�j���O�E�f���N���V�[�̑ɂɂ���B
�m���Ƃ�������A�����m���l�@
19���I���t�����X�ɂ�����u�h���t���X�����v�ɂ����āu�m���l�v�Ƃ����p�ꂪ�g��ꂽ�B����́A�R���ƉE���ɔ����Đl���i��Ƃ��������Ŏg���A�ŏ�����u�m���l�v�́u�l���̂��߂ɓ������݁v�Ƃ��Ďg�p���ꂽ�Ƃ����I�t�q���́A����ɑ����ăm�[�}�E�t�B�[���h�̎��̌��t���Љ���B
�@�u���Â��v���̂́A���̍��̃A�J�f�~�Y���̑Ӗ����B80�A90�N��̃��x�����h�m���l���A�ǂꂾ����ʎs�������̌�����ӂ��Ă����̂��B���Ȃ��Ȃ��܂܂̃c�P�����܂�A���܂��肩���錾�t������I�Ɏ����Ă��܂����v�B
�@���̂��Ƃ́A���������ۑ�w�������������������̑�w�W�҂̕��͋C�ł�����A�܂����̎�����w�A����ɂ͓Ɨ��s���@�l���ɑ��鑽���̍�����w�W�҂̂��Ƃ��w���Ă��邱�Ƃ��Ǝv����B�����A70�N��㔼�ȍ~�}���ɍL�܂����|�X�g���_�j�Y���I�����́u�w��͖��͂ł���v�Ƃ������E�\�z�i�������̉�́j������钆�ŁA�m���͌��t�̗V�Y�Ɖ����B�I���́A�u�����Ƃ����͖̂\�́i�m���Ƃ�������j���s�g���邱�Ƃ����ł��Ȃ����݂Ȃ̂ł���Ƃ����F���ɗ����Ă͂��߂Ȃ�������Ȃ��v�Ƃ����s�G�[���E�u���f���[�̌��t�����p�����B�����āA���́A�u���̉����t����ꂽ���̂˕Ԃ��͂��w���ɂ���Ȃ�A���̋����͓�������Ă����āA���V�����m���ɓ��B���邱�Ƃ��ł���B�������Ȃ���A�ǂ��炪���������킩��Ȃ�����ǂ��A���Ȃ��̍l���������̂ł͂Ȃ��̂ƌ����܂ܕ��u����Ă��܂����w���́A���ɐi�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��v�ƌ��_�Â����B����͎���́u�ӔC�ϗ��v�����������w�l�ł���A�A�J�f�~�Y���̑Ӗ��A�u����Ȃ��m���l�v�ł���Ǝ��͎v���B�l�I���x�����Y���Ƃ�����Ɠ����m���l�u���f���[�́A�w����܂ޕ����̗̈�Ɍo�ς̗̈悪�y���œ��ݍ��ތ����Ɠ����B�w��̕]�����A�u������̊l���z�v�ɂ������A���ʂ̏グ�₷�����ؓI�����ɕ�����A�R���s���[�^�����ɂ������Ƃ��炵���f�[�^�����s������Ƃ������������i�s���Ă���B�܂��A�u����Ƃ��Ă̒m���v���u���ׂ��̒m���v�ւƕϖe�𐋂��Ă���B�����ł́A�m���l�̘A�т̏ꂪ�w����e�i�����j�����̂���Ă������ƂɂȂ��Ă���B�u�����g�݁v�A�u�����g�݁v�Ƃ����\������w�̒��ł����R�Ǝg���n�߂Ă���B���������ۑ�w�����̖{���́A�l�������͂��ߊw����e�̕]�����܂߁A����炪�w���֏W������A�w���ɑg����҂��u�����g�݁v�ł���A�w���ɑg���Ȃ��҂��r������Ă����u�����g�݁v�i�N�r�j�ƂȂ�Ƃ������Ƃł���B�I���́A�u�m���l�͓������ł����Ă͍���B��w�l�͋���҂ł�����B����҂������̃N�r������ē������ɂȂ��Ă��܂��B���̒��ŋ������w���قǕs�K�ȑ��݂͂Ȃ��B�������͊O�Ɍ������Ėڂ��J���Ă����B���̂悤�ȃl�b�g���[�N���������n���Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������t�Œ��߂��������B����ƂȂ��ċv�����u�m���l�v�A�������A���̍Ę_�ƌ��������Җ]�����B���������ۑ�w�����́u�m���l�v�Ƃ͈�̂ǂ����������݂ł��邩�����炽�߂Ė₤�Ă���B����Ɍ}�����A�̐��Ɍ}�����A�g�D�Ɍ}�����A���ɂ͌��͂Ɍ}������m���ƒm���l�̂���l�i��́j�Ƃ�����肪�Ȃ��������Ă���B
�u�m�̊�Ƒ́v�A��卑�ƃv���W�F�N�g
���{�o�ς̊������̂��߂̑�w���v�A�Y���w�Z���A��w�̎����i�Ɨ����j�̉�̂ł���A�w��̗̈�ւ̌o�ς̗̈悩��̐N�I�Ƃ������Ƃ��A��卑�ƃv���W�F�N�g�Ƃ��Ď��g�܂�悤�Ƃ��Ă���B���̂��߂̉��v�́A�܂��������W������w���𒆐S�Ƃ���o�c���c��ɂ��g�b�v�_�E�����s����悤�ɂȂ�B�o�c���c��Ƌ��猤���]�c���̑�\�ɂ���Ċw���I�l��c���ݒu�����B����܂ł̋��E���Q���ɂ��w���I���ł͂Ȃ��A���̑I�l��c�������I�Ȋw���I�l�ɂ����邱�ƂɂȂ�B��������w�����I���ƁA�w���̈ӌ��Ŋw�����I�l���s���o�c���c������猤���]�c��̃����o�[���w���̈ӌ������f����邱�ƂɂȂ�B����ɕ����Ȋw�Ȃ̉��ɂ���]���ψ���A�o�c�̊ϓ_����������̕]�����s���A�]���̒Ⴂ�w���͕����Ȋw��b�ɂ���ĉ�C����邱�ƂɂȂ�B�����Ȋw��b�������ǂ����w�^�c�̃g�b�v�Ƃ��ČN�Ղ���B���́u�m�̊�Ƒ́v�A���Ƃ��Ắu������w�@�l�v�͕����Ȋw��b���g�b�v�ɂ��ĉ^�c������卑�ƃv���W�F�N�g�ł���B�r�������́A�u�m�̊�Ƒ́v�ւ̕ϖe���������Ƃ��Ă̑�w�̘_����r������Ƃ��A�����Ɋ�^����w��i���͂�����u���w�v�ɑ���u���w�v�Ƃ���j�̔r������卑�ƃv���W�F�N�g�Ƃ��Đ��i����悤�Ƃ��Ă���ƌx�������B���������ۑ�w���ł̊��������x�z�̐��i���w���ł̂��̊Ԃ̊w�������̋����Ɋ�Â��V���ȉ^�c�̐��Â���j�͂��̍��ƃv���W�F�N�g�̗���ɐ�s���Ă���B�w��̕]�����w�����s���A���̕]���ɍ���Ȃ��ꍇ�͋�����ʼn����ꂽ�l�����p�������B����݂̂Ȃ炸�A���̂悤�Ȑl����i�߂����������ق��邱�ƂɂȂ��Ă���B�w��̎��R����т��̐��x���Ƃ��Ă̑�w�����̒S����͊w���ƂȂ�B���̂��Ƃ͈ꎭ�������ۑ�w�݂̂Ȃ炸���㑽���̑�w�^�c�ɂ����Č��O�������ł���B���������ۑ�w�����̑�O�̖�萫�i�́u�m���Y����v�g�D�̂̌o�c�E�^�c�̂���l�̖��ł���B�����ł͐l�����ƂƂ��Ɂu�m�Ƃ͉����v�̍��{������Ă���B
�s���I���R�̐���
������w�ɂ�����o�c����𗝗R�Ƃ������فE�l�������A������w�ւ̔ᔻ�ɂ����فA�@���s���ւ̎Q�����ۂɂ�鏈���A�g�������E�g�����ւ̌����点�E�e���A������ʁA�����E�ւ̔z�u�����A�u�������i���~�S�j�̑��݂ȂǁA�Љ�I�ɔF�߂��Ă���s���I���R�̐�������w���ōs���Ă���B�l�ѐ��v���́A���{�̍����S�̂��s���I�����A�l����N�Q����Ă��錻��Ƃ̊ւ�肪�d�v�ł���A�s���I���R�̓y�䂪���{�Љ�S�̂Ƃ��ĕ�����钆�ŁA��w�ł̐l���N�Q���i�s���Ă���Ƌ��������B�܂��A����܂ő�w�l�͌����N�Q�ɑ���ӎ����キ�A���݂̎��ԂɗL���ɑΉ��ł��Ă��Ȃ��B�N�Q����̂قƂ�ǂ��\�ɏo�Ă��Ȃ�����������A�{�l����ю��͂������グ��K�v������B���́A���̂��߂ɂ��S���I�ȘA�сi�l�b�g���[�N�j���������߂��Ă���Ƃ��ꂽ�B�V���ȑ�w�Â��肪���낢��ȗ��ꂩ�珥�����A�����邢�͌X�̎�����w�ŋ�̓I�ȉ��v���s���Ă���B���̒��ŋ���E�������e������I�ɉ��҂���A�����Ɏs���I����������������Ă����Ƃ������Ƃ��������X�ƍs����悤�ɂȂ��Ă��Ă���B���������ۑ�w�����ł́A�g�b�v���u���ۉ��v�Ƃ��u��w�@�d���v�Ƃ������j���f���A����܂ł̒~�ς�n������Ȃǂ����Ĉ���I�ɉ��v���i�߂��Ă����B�����ł͖����`�̐[���E�O��Ƌt�s���鎖�Ԃ��i�s���Ă���B�܂�A���|�����������Ȃ��狳��E�����A����ɐl���������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ُ�Ȏ��Ԃ��i�s���Ă���B������������ɑ��āA��X�����ۓI�E��ʓI�Ɂu�����̂��߂̑�w�Â���v�A�u�J���ꂽ��w�Â���v�Ƃ����Ă����߂ŁA��͂�w��̎��R�Ɋ�b�Â���ꂽ�������E���猠�ɂ����v���s���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���l�X�R�̏������͂��̈Ӗ��ŏd�v�ł���B��������̍��ۓI��i�O���[�o���E�X�^���_�[�h�j�͖��m�ɂȂ��Ă���A��������s���I�������𐧌����o�ϓI����������w��Ƒ�w���ĕ҂��悤�Ƃ��Ă���W���p�j�[�Y�E�X�^���_�[�h�̌�����ᔻ���Ă����K�v������B�C�����ɂ��Ă��A����ł͓��Ɏ�茤���҂̎g���̂Ă̂悤�Ȍ���������A�܂����u�t�̗ȋ���E���������͖��炩�ɐl�����ł���B�Ⴆ�A���l�X�R������u�I�g�ݐE���v�Ƃ�������I�Ȑg���ۏႪ�w��̔��W�ɂƂ��ďd�v�ł���Ƃ����l���͂��łɃO���[�o���E�X�^���_�[�h�ƂȂ��Ă���B����E���������Đ��������D���邩���뜜���Ȃ���A�܂Ƃ��ȋ���E�������s���邱�Ƃ͊��҂ł��Ȃ��B���������ۑ�w�����̑�l�̖��͎s���I���R�̐����ł���B
�Ō��
�@���A��w�l�̓��X�g���i���j�����|���铭���l�����Ɠ��l�̋��|�̒��ɂ���B�Ɨ��s���@�l�������߂�������w�W�҂����l�ł��낤�B���炩�ɂ��̍��͍��u�w��̎��v���}���悤�Ƃ��Ă���B�e��w�ԋ����́u�����v�̒��Ő����c������w���u������w�v�ł���A�����Ȃ��悤�Ɋ撣��Ƃ����̂���w�o�c�̊�{�ɂ�����Ă��錻��������B�u�����I���̒��Ō����P����w�v�ȂǂƂ����������������Ȋw�Ȃ̃L���b�`�t���[�Y���܂��Ƃ��₩�ɏ������A���̋����ɏ���������u�����v���w�ɋ��߂Ă���B���̋����ɓ���Ȃ��w��A�܂������Ă������Ă��܂��w��́A���̊w��̌��ƂƂ��ɂ��̒S����ł��鋳�����r������Ă������ƂɂȂ�B�{���A���͋���������̂ł͂Ȃ�����������̂ł���B���̋����̋����̒��Ɍ��R�ƍ��ʂ��s����B�����ɏ����������߂ɖړI�i�����͌o�ϓI�ł��茠�Ў�`�I�ړI�j������I�ɗ��Ă��A���̖ړI�̂��߂ɋ���E�������e����ѐl�����i�߂���B�����ł́A�s���Ȉ�������҂���������A���̐l���݂Ď���͈ޏk�����|����B���łɂ��̈ޏk�Ƌ��|�̘A���͑�w���ɂ����ĎЉ�ɖ������Ă���B����ɑ��A�������L�������I�ȉ��l�i���j�������ł���ϋɓI�Ȏd�g�݁i�l�b�g���[�N�j���w���O�ō���Ă����K�v������B����̃V���|�W���E���ł̋��E���g���A�w��A�Ȋw�Ғc�́A���̎x���c�́A�����āu�O�������x������S���A����v�̘A�g�͂����������݂̃l�b�g���[�N�ł���B����A���̃l�b�g���[�N�͍������獑�ۓI�ȍL����������Ƃ��낤�B�����������Ŏ��������ۑ�w�́u���|����̎��R�v���l�����邱�ƂɂȂ邾�낤�B���������ۑ�w�����̉�����21���I�̓��{�̑�w�Â���̎����ł���B
�i�������ƂȂ��Ƃ��@���������ۑ�w�O�������x������S���A������ǒ��@���J��w�j
|